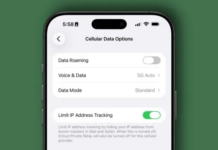フォトグラファーのたかはしじゅんいちです。東京工芸大で2年間写真のお勉強をして(写真の写り方をかじって)、日本を代表する写真家・立木義浩の弟子を4年半して、色々なカメラの使い方やライティング、モノクロプリントの技術、業界のマナーなどを学びました。その後独立してニューヨークへ単身渡米。1989年、つまり平成元年のことでした。そこから19年間はニューヨークにどっぷりで、多種多様な方々と一緒に仕事をして感性を磨き、2009年からは東京ベースで仕事をしています。
キャリアをスタートさせたのはもちろんフィルムの時代。アシスタント時代は昭和の話ですからね。時間経過が恐ろしい(笑)。当時の業界では割と平均的な経歴だと思います。
立木さんの下で、撮影技術やマナーをトコトン学んだ20代。この経験は、その後に繋がる大きな財産になりました。初任給:50,000円という、丁稚奉公のように厳しい生活でしたが(笑)、あの時に学んだ技術は世界で通用する“技術”。ニューヨークへ渡ってもすぐに現地の仕事を貰えたのは、まさにその“技術”あってこそだと思います。
ニューヨークで切磋琢磨出来たことも私の財産です。世界の一流どころ、例えばジェニファーロペスやロバートデニーロ、STOMPやワダエミさんらと仕事をする中で、たくさんの刺激をいただきながら、物創りの仕方や自分らしさを探求することが出来ました。
もちろん厳しい環境ではあります。
「君を雇うメリットは?」
「君は私たちに何を提供出来るの?」
そうした問いに、日々応えていかなければなりません。しかしその中で、自分を形作れて行けたと思いますし、「楽しむ」ことも学べたと思います。
スマホでインスタの時代における「写真家の仕事」
言わずもがなですが、写真はいま、デジタルの時代。スマートフォンで撮影した写真がSNSを駆け巡ります。
プロ向けのカメラも進化して、写真を撮るのはとても簡単になりました。ある程度のことはカメラがやってくれますし、暗いところでもきちんと写るので、ライティング技術を学ぶ必要も、昔ほどはありません。
撮影機材は日進月歩で、写真を撮ることもまた、日に日に特殊技術ではなくなっていく……。ちょっとかじれば、誰でもいい感じの写真が撮れる、そんな時代です。
だからこそ、昔よりも「感性」が大事になっていると思います。「技術」の差がカメラの進歩で縮まっているからこそ、写真の仕上がりには撮影者の感性が、ダイレクトに現れてしまうわけですね。
「感じる」心の感度、「観る」力。これをどう養い、高めるか。
当然ですが、感じられないものを見ることは出来ませんし、見えないものを写すことも出来ません。なので、心の感度を上げて、様々なものを感じられるようにならないといけない。
感じた物事をよく見て、見えたモノをカメラなどで「写す」。このプロセスこそが、今の時代に写真を撮ることであり、重要なテーマだと思うのです。
……って、ちょっと言い回しがお堅いですね(笑)。しかし、これはプロのフォトグラファーとしてこれからも仕事をしていきたいと思う私にとっては切実なる想いであり、現実でもあります。
私の「Afterimage-残像」という作品群は、こうしたテーマを意識的に捉え、「気配」とか「時間」を写し込もうと試んでいる作品たちです。
私には、そこにいたであろう気配を感じられ、ここが部屋として機能していた時間を想像出来ています。
自分が感じているものを、きちんと写真に写し込めているか。
撮影技術がフラット化している今だからこそ、この基準をプロのフォトグラファーは必ずクリアしなくてはならない、そう思うのです。
変化、進化が求められるフォトグラファー
「状況が良い時に良い写真が撮れるのは当たり前なんだよ。状況が悪い時に何が撮れるのか、それでも目的にあった良い写真が撮れるのがプロの価値なんだよ」
師匠・立木義浩の言葉です。
フォトグラファーという仕事の、社会的な位置付けや存在意義が時代とともに変化する中で、自分の中の何を柔軟に変化させて、何を大切に守っていくのか。それこそが、これからの自分をブランディングするものになると考えます。……とはいえ、私自身も正解を持っていません(笑)。いやー、厳しいです、いま置かれている我々の環境は。
だからこそ、今はとにかく試行錯誤。考え、実行し続ける毎日です。まだまだ道半ばなたかはしですが、この連載ではこれからの時代におけるフォトグラファーの役割や、学び方を考えていければと思います。