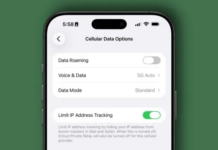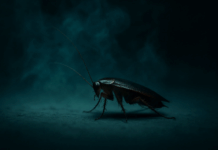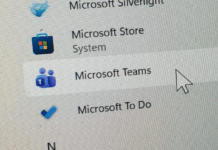皆さんこんにちは。河上 純二 a.k.a JJです。

B DASH CAMP 2025 Fall in Fukuokaが2025年11月5日〜7日にヒルトン福岡シーホークを会場に開催。Ubergizmo Japanでは今回もイベントに参加してレポートします。
オープニング・セッションである「「スタートアップの成長はどこへ向かうのか(2025秋編)」」をいち早くレポート。

今回のテーマは「Path to Wininng(勝ち筋を探せ!」。
GPU争奪戦、エネルギー再設計、3年後のアプリ覇権、日本のスタートアップ/株式市場で、AI・ディープテックをめぐる潮流が再び熱を帯びている。だがその進化は、単純な「生成AIブーム」では終わらない。GPU調達・データセンター整備・エネルギー供給の“三位一体インフラ”が今後の命運を左右する――そんな現実が鮮明になりつつある。
=登壇者=
■スピーカー
武田 純人(野村證券)
辻 庸介(マネーフォワード)
宮澤 弦(LINEヤフー)
■モデレーター
渡辺 洋行(B Dash Ventures)
◆ 市場環境:テーマ偏重の二極化、グロースは再評価へ
日経平均は上昇を続けているが、その裏で「勝てる銘柄はさらに勝ち、その他は埋没」という二極化が進んでいる。
突出した成長テーマを掲げ、かつ規模を持つ企業だけが、株式市場で“トップギア”に入った状態でアウトパフォームする構図だ。

一方、スタートアップを取り巻く資金調達には逆風が吹く。IPO件数は鈍化し、グロース市場の勢いも後退。VC投資も前年から半減ペースで、「テーマ不在」の局面が続く。
投資家心理は米国のAIインフラ投資――NVIDIAを中心とした “Magnificent Seven”―へ乗り遅れるリスクを懸念しており、「欧米経済圏との接続性」が企業評価を決定づける重要要素となっている。
◆ GPU戦争の現実:インフラ構築が勝敗を決める
AI・ディープテックが進む上で、現在の最大ボトルネックはGPU調達だ。
GPU調達枚数の観点で、日本は韓国を含む海外勢に後れを取っている。データセンターの拡充も急務で、そこで問題になるのが冷却技術と電力供給だ。
特に電力は再エネ・原子力を含む総合的なアップデートが必要。
韓国のように政府がGPU調達を支援するケースも出ており、国家的な後押しがなければ、そもそも競争のスタートラインに立てないという厳しい状況が浮かぶ。
しかし、日本にはニッチ領域で光る素材力がある。
液浸冷却に使われる特殊素材、あるいはAI×ロボティクスで求められる関節制御など、世界需要が急成長する「部品・材料」の分野で存在感を発揮できる可能性が高い。この“エコシステムの解像度”を上げることこそ、産業全体の競争力につながる。

◆ 2〜3年後に花咲く「アプリケーションレイヤー」の巨大市場
足元のGPU・電力整備は、言わば “レール敷設期”。その先に本格化するのがアプリケーション層の競争だ。いまはまだ序章にすぎない。
例えば、産業現場のオペレーション知識を統合したAIや、病院の診療フロー、製造ラインの調整、物流・金融・教育など、縦割りの現場知識が今後価値の源泉になる。
これを“現場AI(Domain-Integrated AI)”と位置づけるならば、北米でのYouTube台頭がブロードバンド普及の後だったように、インフラ普及が進んだ先に巨大な価値が生まれる。
もちろん、B2C領域にも大きな余白がある。暮らしを直接豊かにするAIアプリ、生活圏をスムーズにつなぐデジタル体験。現時点では未開拓ゾーンが多く、チャンスは計り知れない。
◆ SaaSは“再定義”される
従来のSaaSは、UIを中心とした表層最適化が主戦場だった。だが生成AIがもたらす再編は、ロジック層・データ層までを含む再設計を迫る。
もはや「SaaS企業ではなく、AI企業」と位置づけるべき時代へ。
UIレイヤーでの生成AIはすでに浸透しつつあるが、真の競争優位は、「深いロジック + 産業データ」
を組み上げられる企業が握る。
◆ 国家戦略:地政学×国産化×省庁調達
半導体からAIまで、「国産技術で固める」動きが強まっている。
グローバルサプライチェーンが再編される中で、経済安全保障の文脈が企業成長のレールを引く。
特に政府調達は重要だ。
中長期の投資を支える需要創出装置として、官民連携は不可避。民間単独では不可能なスケールのインフラ投資をどう支えるか?その回答が国家連携にある。
◆ 国内市場 × 地方 × 体験産業
日本市場においては、上場を通じた長期対話が企業成長の重要ステップになる。
一方、地方にはロールアップによるスケールの余地が残る。
寿司や高級飲食、エンタメといった「人×体験」産業は、テクノロジーによって再編集される余地が大きい。
◆ 海外展開:東南アジアが金脈
中長期で見れば、東南アジア市場は大きな伸びしろを持つ。
日本で事業実績を積み、経済安全保障の文脈も活かしながら進出する形が現実的だ。
国ごとの規制の隙間こそ勝機があり、サービスのローカライズ設計が成否を左右する。
◆ 周辺テーマ:エネルギー・量子・ステーブルコイン
AIインフラ整備は、電力需要を爆発的に押し上げる。
今後10年で国内データセンター電力需要は約3倍に膨らむとの試算もある。
再エネ・原発を含むエネルギーインフラの再構築は避けて通れない。
さらにAIの次の地平として、量子コンピュータが浮上する。
また、ステーブルコインは決済/金融インフラを塗り替える可能性を持ち、制度整備が進みつつある日本は参入余地が大きい。
◆ 結論:3年後のアプリ覇権へ
未来は明るい――ただし、レール敷設を完了できた者だけが、その先の巨大市場に立てる。
日本の勝ち筋は明確だ。
•国産インフラの整備
•ニッチ領域の競争力を活用
•安保文脈を追い風に長期投資
•アプリケーションレイヤーでの産業実装
•官民連携で調達力・実行力を強化
3年スパンでやってくるアプリケーションの“収穫期”を見据え、今は基盤を敷くフェーズ。
GPU争奪戦、データセンター拡張、電力再設計といったそのすべてが未来の勝者を決める。
日本は、まだ勝てる。