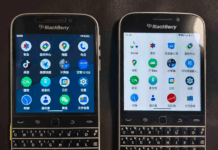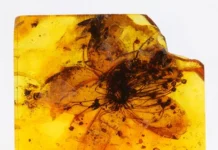中国のEV大手 BYD(比亞迪) が、次世代バッテリー技術として注目される 全固体電池(Solid-State Battery, SSB) を搭載した電気自動車(EV)を、2027年に投入する計画をあらためて明らかにしました。今回の動きは、EV業界における技術競争での大きな転換点になりうるものです。 

⚡ 全固体電池の優位性と技術目標
全固体電池は、従来のリチウムイオン電池に比べて 安全性・熱安定性・エネルギー密度 に優れるとされます。液体電解質を使わない構造により、発火・液漏れの危険を減らすことが期待され、さらに構造の薄型化なども可能になります。 
BYD の目標スペックとしては、400 Wh/kg のエネルギー密度を達成することが挙げられており、これは現在の主流バッテリー(LFP や NMC など)を大きく上回る水準です。  また、レンジ(航続距離)は 800 km 超を目指す見込みも出ており、近い将来には 1,000 km クラス も視野に入れられています。 
さらに、充電速度に関しては たった12分で満充電 に近づく可能性も報じられており、ユーザーの利便性向上に直結する規格革新として注目を集めています。 
🗓 導入スケジュールと展開フェーズ
BYD の CTO によれば、2027年から限定モデルを用いた デモ導入(実証運用) を開始し、2027〜2029年を実用化の試験期間と位置付けています。  そして、2030年あたりから本格的な 量産体制・普及フェーズ に移行する見通しが語られています。 
この段階的展開には、市場やコスト・製造技術の成熟具合を見ながら慎重に進める戦略が見え隠れします。なお、初期導入は主に上級モデル向けとされ、普及モデルへの展開は後段階と見られています。 
⚠ 技術・実用化に向けた課題
全固体電池は理論上の優位性が高く期待も大きいですが、商用化までにクリアすべき課題も少なくありません:
•コスト高:精密な製造プロセスや高性能材料の採用が不可避であり、従来型電池より高コストとなる可能性。 
•界面抵抗・イオン伝導性:固体電解質と電極間の接触抵抗、低温動作時のイオン移動速度低下など、技術的なハードルが存在。 
•耐久性・劣化特性:繰り返し充放電や温度変化に対する耐性、寿命設計が実運用に見合うレベルであるか。
•インフラ整備:超高速充電器や対応端末、充電網強化といった周辺インフラの導入が不可欠。
•実証データの信頼性:現段階では公表されているのは“目標値” や“見込み” レベルのものであり、実測データがまだ限られている点。
BYD 自身も、供給量・製造能力・コスト低減のための基地整備(たとえば重慶の拠点)などを含む計画を進めていることが、公開情報から読み取れます。 
✅ 総評:EV時代の鍵を握る挑戦
BYD が掲げる全固体電池搭載 EV の導入構想は、EV 業界の “次のステージ” を定義する挑戦的な取り組みです。もし計画どおり技術と実用性を両立できれば、航続距離・充電時間・安全性の改善という三拍子揃った変革をもたらし、多くの EV にとって「不安材料」であった壁を一気に引き下げる可能性があります。
ただし、論理値と実測値とのギャップ、技術課題・量産化の壁、コストと普及性のバランスといった現実要素にどう対応するかが成功を分ける鍵となるでしょう。ガジェット好き・EV好きの目線で言えば、2027〜2030年あたりの製品投入・性能実証の結果が、この新バッテリー時代の勢力図を大きく変える可能性を秘めています。